今年の「祇園さん」が、7月の連休に2日に亘って開催された。
昔は3日間に亘って、挙行されたもの。
「祇園さん」は、郷土の神社「須佐神社」に伝わる、唯一の夏祭り。
かれこれ500年に亘って営まれる、県北では珍しい伝統的な祭事。
「大神輿」は県重要文化財に、指定されている。
「大神輿」の移動は、夏祭りの一大イベント。
恐らく、田植えも終わり、泥落としも兼ねて、五穀豊穣を祈願する祭りなのだろう。
「祇園さん」に由来するように、京都の「八坂神社」に、由来するものと思われる。
1日目は、近隣の矢野地区が担当、2日目は郷土の小童(ヒチ)地区が担当。
私の子供の頃は、相当な賑わいで、近隣の1市3郡から、挙って多数が参拝。
街並みを行き交う客で、肩がすれ違う程の、人の群れだった。
祭りには、子供の私も太鼓を叩いて、参加したもの。
確か、100円位の小遣いを貰い、後から友達と、露店を亘り歩いた。
夜には、夜店も出て賑わっていた。
確か、芝居小屋が立って、昼間は拡声器が音を張上げて宣伝し、祭りのムードは最高頂。
当時は、ラムネが美味しくて、開けるとき、ボンと音を立てて泡が吹いた。
それが珍しく、一番に買い求めた。
「かけ氷」もあり、赤や青の色付けされたのを見ると、堪らなく欲しかった。
そんな昔を想起しながら、門前を歩いていたら、Mさん家族が自宅を開放して、丁度「かけ氷」を販売中。
Mさんは、小学校の同級生。
思い出したように、お互いに声を掛け合い、昔話に花が咲いた。
思わず、その場で「かけ氷」を注文、縁側で休みながら、行き交う人を眺めていた。
旧知の仲の人もいて、遠目で挨拶することだった。
矢張り、郷土の夏祭りだけに、「祭魂」と記した法被を着た、威勢のいい若者が、数人元気よく通り過ぎる。
祭りを盛り上げる、掛け替えのない青年達だった。
私も、足の痛みを感じながら、後を追うた。
祭りの最後に、人力で大きな神輿(県重要文化財)を500~600m、本殿に移動する祭事がある。
本殿の急坂な坂道でも、人力で引っ張り、納庫する。
皆の力を結集し、団結なしには出来ない。
お陰でこの地区は、これ迄“コミュニティがよくまとまっている”と皆に言われきた。
この度の「祇園さん」では、懐かしい昔のあれこれが思い出された次第。
「かけ氷」は、子ども時代からの念願、それが叶った。
矢張り、繋がりが大事だ!
人は思い出に生きる!





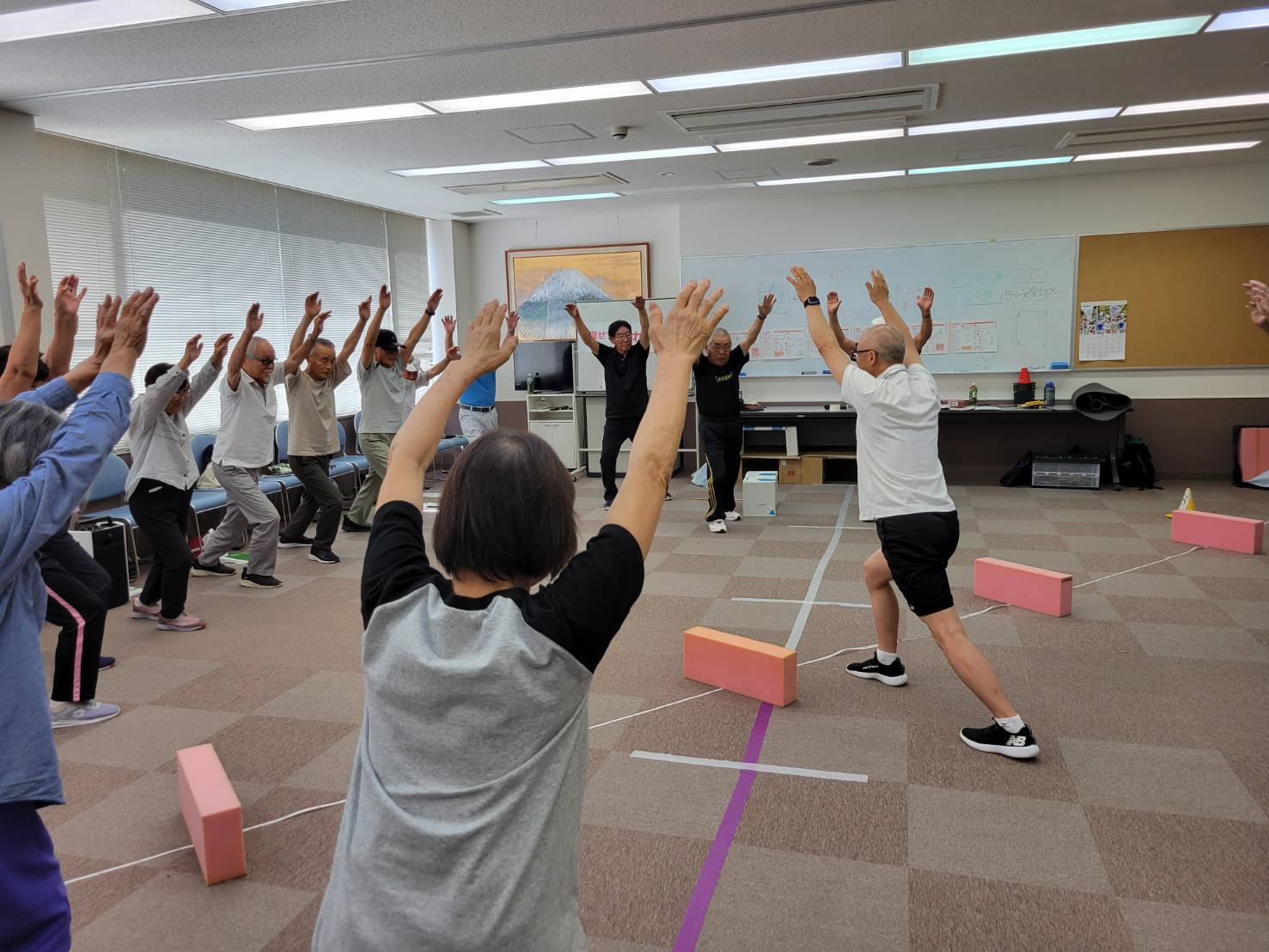
コメント